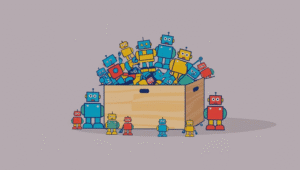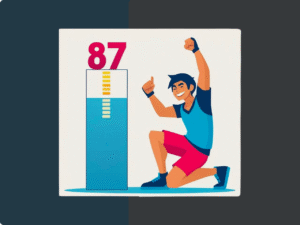今日も今日とて向かう先は同じ。毎日通うこの中央線一号車、24時間経てどついさっきまでここにいたような気さえ思える。さて、本日は連勤最終日、明日は待ちに待った休日。のはずなんだが。なぜだろう、オレの心は微塵も浮かれる素振りを見せようとしない。
今は全てがどうでもいい。予定の電車を一本乗り過ごしてしまったことも、車内で大声で話す外国人も、車窓に映る寝癖が見窄らしいオレも。同じ空間にいるのにオレ一人だけが違う空気を吸っているような、不思議な感覚。視界に入る景色も耳に入る雑音も、表面を流れるだけで決してオレの意識を通過しない。しかし乗り換え駅到着の車内アナウンスだけは意識的に聞き取ろうとするのだから、オレの脳みそはすでに何かに支配されつつある。
乗り換え駅のホームにて、偶然目に留まった広告。特に目立つわけでもないペット保育園のただの広告。そこには満面の笑みを浮かべるフレンチブルドッグの写真が写されていた。ただ、それだけなのに。なぜかわからないまま、急に笑いが込み上げてくる。その一瞬時が止まったように感じた。実際、時間にすればたった数秒だたろうが、広告を前に立ち止まり自分の世界で笑い続けた。
「そうか、そうだ、そうだよな。おれ、疲れてんだわ笑」
それがわかった瞬間から、体がスッと軽くなっていく。自暴自棄で全てを投げ出すような感覚じゃない、今まで背負っていた重たい荷物を一度背中から下ろすだけのような感覚。今、オレの周りを通る人間たちが広告を前に笑うオレを見てどう思っているのか、おれはどう思われているのか、そもそも見られているのか。大都会、通勤ラッシュのど真ん中でそんな思考が過ぎるが何も気にならない。いや、気にするほどのことでもないことに気がついたんだ。ストレスは気がつかない程度で塵積もり、気づいた時には押しつぶされている。いや押しつぶされていることにさえ気がつかず潰されてしまうことの方が多い。まるで、常温から茹でられるカエルのように。だからこそ、ふとしたときに背負ってるものを下ろしてみる。何気ないものに救われるっていうことは本当にあるもんだ。
「そんなに重たいものを背負ってどこにいくんだい。それじゃ芝生さえも走り回れないじゃないか。身軽になれば走っているだけで楽しくて笑えちゃうんだじぇ。」
広告に映るブサイクながらも愛おしいその笑顔がオレに問いかけてきた気がした。
さあ、そろそろいかなきゃ。
ついてないの一言で片付けられないような最悪な日も、開き直ろうが抱え込もうが”二度と来ない今日”だとわかれば、それはそれで案外笑えちゃうよな。明日の休日、目的もなしに遠くの土地にいってみるもの悪くないかな。
今日も今日とて、向かう先は同じだ。 レールの継ぎ目を刻む、ガタン、ゴトンという無機質なリズム。中央線一号車の隅、ドア横の手すりにもたれかかりながら、私は薄汚れた窓の外を流れるコンクリートの壁を眺めていた。
毎日通うこの場所。二十四時間が経過しているはずなのに、ついさっきまでここにいたような気さえしてくる。昨日も一昨日も、その前の日も、私はこの車両のこの位置で、同じ吊り革の揺れを見ていた。まるで録画された映像を何度も再生されているような、あるいは時間のループに閉じ込められたような錯覚。
「次は、新宿、新宿です」
アナウンスの声もまた、昨日聞いたそれとまったく同じトーンで鼓膜を震わせる。 さて、本日は地獄のような連勤の最終日だ。この電車を降り、会社へ向かい、あと十数時間ほど身を削れば、明日は待ちに待った休日。泥のように眠るもよし、溜まった洗濯物を片付けるもよし。本来であれば、その解放感を前に少しは心が浮き立ってもいいはずだった。
なのに、なぜだろう。 オレの心は微塵も浮かれる素振りを見せようとしない。 胸の奥にあるはずの「感情」という名のエンジンが、ガス欠を起こして冷え切っている。休日というガソリンを目の前にぶら下げられても、点火する火花すら散らないのだ。
「……はぁ」
ため息をつくことさえ億劫で、息を吐く動作を途中でやめる。 今は全てがどうでもいい。
今朝、予定していた電車を一本乗り過ごしてしまったことも、そうだ。以前の私なら舌打ちの一つもしていただろう。「遅刻はしないが、始業前のコーヒータイムが削られる」とイライラしながら時計を睨んでいたはずだ。だが今日は、「ああ、行ってしまったな」と、落ち葉が風に流されるのを見る程度の感想しか抱かなかった。
車内は混んでいる。私のすぐ背後では、大きなキャリーケースを持った外国人観光客のグループが、楽しげに、そして遠慮のない大声で会話を繰り広げている。普段なら「もう少しトーンを落としてくれ」と眉をひそめる場面かもしれない。しかし、彼らの歓声もまた、私の意識のフィルターを素通りしていく。彼らは「旅行」という彩り豊かな世界に生きていて、私は「労働」という灰色の世界に生きている。同じ空間に物理的に存在しているのに、自分一人だけが違う成分の空気を吸っているような、奇妙で浮遊感のある感覚。
ふと、トンネルに入った瞬間、窓ガラスが鏡代わりになり、自分の顔が映し出された。 そこには、見窄らしい寝癖をつけた、生気のない男が立っていた。 ひどい顔だ、と他人事のように思う。ネクタイは少し曲がっているし、目の下には隈がある。けれど、それを直そうと手が動くことはない。視界に入る景色も、耳に入る雑音も、すべてが表面を流れる水のように滑り落ちていく。私の意識の核には何一つ浸透してこない。
世界と自分との間に、透明で分厚いアクリル板が一枚挟まっているようだ。 誰かが私にぶつかっても、私が誰かの足を踏んでも、今の私なら「無」のままやり過ごせる気がした。感覚が死滅しつつある。
しかし、不思議なものだ。 そんな幽霊のような状態であっても、「次は〇〇、お乗り換えです」という乗り換え駅到着の車内アナウンスだけは、オレの脳みそが勝手に拾い上げ、身体に命令を下す準備を始めるのだから。 右足を出して、左足を出す。改札へ向かう。階段を登る。 オレの脳みそは、すでに自分の意志ではない「何か」――社会の歯車としてのプログラムに、完全に支配されつつあるらしかった。
人波に流されるままホームに降り立つ。 次の電車が来るまでの数分間、私はホームの柱の影に避難するように立った。 視線のやり場に困り、ぼんやりと顔を上げる。
そこで、偶然、それが目に留まった。
駅のホームには無数の広告が溢れている。脱毛クリニック、英会話教室、週刊誌のゴシップ見出し。情報の洪水だ。 だが、私の視線を捉えて離さなかったのは、それらの中で特に目立つわけでもない、こじんまりとした看板だった。 『ワンちゃんの保育園、はじめました』 そんなありきたりなキャッチコピーと共に載せられていたのは、一匹のフレンチブルドッグの写真。
ただ、それだけだった。 洗練されたデザインでもなければ、奇をてらったコピーでもない。 ただ、その写真の中の犬は、これ以上ないというほどの満面の笑みを浮かべていた。 口を大きく横に広げ、舌をだらしなく垂らし、目は糸のように細くなっている。クシャクシャのシワだらけの顔。威厳のかけらもない、愛嬌だけを煮詰めたようなその表情。
それを見た瞬間。 ドクン、と心臓が大きく跳ねた気がした。
「…………」
なぜかわからないまま、急に笑いが込み上げてくる。 最初は喉の奥でくぐもった音だったものが、我慢できずに口元から漏れ出した。
「ふ、ふふ……」
その一瞬、時が止まったように感じた。 周囲を行き交うサラリーマンの革靴の音も、発車ベルのけたたましい音も、すべてが遠い彼方へ追いやられた。 実際、時間にすればたった数秒だっただろう。だが、私はその広告を前に立ち止まり、自分の世界で笑い続けた。 肩が震え、口角が持ち上がる。乾いたスポンジに水が染み込むように、枯れ果てていたはずの感情が、じわりと温かいものを伴って戻ってくる。
あんなに無表情だった自分が、今はただの犬の写真一枚で笑っている。 その事実が、さらにおかしさを誘う。
「そうか、そうだ、そうだよな。おれ、疲れてんだわ笑」
誰に聞かせるわけでもなく、ぽつりと呟いた。 その言葉が自分の耳に届いた瞬間、魔法が解けたように、あるいは魔法にかかったように、体がスッと軽くなっていくのを感じた。
それは、自暴自棄になって「もうどうにでもなれ」と全てを投げ出すような重たい諦めではない。 ずっと背負い続けて食い込んでいたリュックサックを、ほんの少しの間、ベンチに下ろした時のような感覚。 重荷そのものが消えたわけではない。仕事はまだあるし、責任もなくならない。けれど、「ああ、重かったんだな」と自覚し、一旦下ろすことを許されたような安堵感。
今、オレの周りを通る人間たちが、犬の広告を前にニヤニヤと笑うオレを見てどう思っているのか。 「変なやつがいる」と思われているのか。哀れみの目で見られているのか。そもそも、誰もオレのことなど見ていないのか。 大都会、通勤ラッシュのど真ん中。本来なら他人の視線が突き刺さるような場所だ。 けれど、そんな思考は一瞬頭をよぎっただけで、すぐに霧散した。
何も気にならない。 いや、気にするほどのことでもないことに気がついたんだ。
今まで、オレは何を守ろうとしていたんだろう。 「社会人としてちゃんとしなきゃいけない」「疲れた顔を見せてはいけない」「予定通りに行動しなければならない」。 そんな見えない鎖で、自分自身をがんじがらめに縛り付けていた。
ストレスというのは厄介なものだ。 劇的な悲劇が起きれば、人は「辛い」と叫べる。だが、日々の微細なストレスは、気がつかない程度で塵のように積もっていく。 今日の満員電車が少し暑かったこと。メールの返信が素っ気なかったこと。コンビニのおにぎりが売り切れていたこと。 そんな些細な「不快」が、心のコップに一滴ずつ泥水を垂らしていく。 そして気づいた時には、その重みに押しつぶされている。 いや、押しつぶされていることにさえ気がつかず、潰されて変形したまま生きていることの方が多い。
まるで、常温の水からゆっくりと茹でられるカエルのように。 熱さに気づいた時にはもう、鍋から飛び出す脚力なんて残っていないのだ。
だからこそ。 ふとしたときに、こうして背負ってるものを下ろしてみる必要がある。 自分の意志で鍋の蓋を開け、「熱いじゃないか」と笑い飛ばす時間が必要なのだ。
オレを救ったのは、高尚な哲学書でもなければ、親友からの励ましの言葉でもない。 駅のホームの片隅にある、見ず知らずの犬のブサイクな笑顔だ。 何気ないものに救われるっていうことは、本当にあるもんだ。人生捨てたもんじゃない。
再び、広告の中のフレンチブルドッグと目が合った。 シワシワの顔で、彼は私にこう語りかけてきているような気がした。
「そんなに重たいものを背負ってどこにいくんだい。それじゃ芝生さえも走り回れないじゃないか。身軽になれば走っているだけで楽しくて笑えちゃうんだじぇ」
幻聴だとわかっている。語尾が「だじぇ」なのも、私の勝手なイメージだ。 けれど、その言葉はどんな名言よりも今の私の芯に響いた。
そうだ。芝生を走るのに、立派な鎧はいらない。 目的も、意義も、効率も、時には全部どこかのロッカーに預けてしまえばいい。 ただ走って、転んで、泥だらけになって、それを「あーあ」と笑う。 それが生きるってことじゃないのか。
「……ありがとな」
心の中で犬に礼を言い、私は深呼吸を一つした。 肺に入ってくる空気が、さっきまでとは違って美味しく感じる。雑踏の匂いの中に、微かな冬の匂いが混じっていることにも気づけた。
さあ、そろそろいかなきゃ。 現実は待ってはくれないし、遅刻ギリギリの時間だ。 けれど、足取りは驚くほど軽い。
ついてないの一言で片付けられないような最悪な日も、あるだろう。 理不尽に怒られる日も、自分が情けなくて泣きたくなる夜もあるだろう。 でも、開き直ろうが抱え込もうが、今日は”二度と来ない今日”だ。 そうわかれば、それはそれで案外笑えちゃうよな。
「最悪な一日」という貴重なエピソードトークのネタを手に入れたと思えばいい。 この世界の主人公であるオレの物語に、ちょっとしたスパイスが加わっただけのことだ。
明日の休日。 本来は家で死んだように眠るつもりだったけれど、予定を変更しよう。 目的もなしに、電車に乗って遠くの土地にいってみるのも悪くない。海を見るのもいいし、山を見るのもいい。あるいは、知らない街の商店街でコロッケを買い食いするだけでもいい。 「意味のないこと」を全力でやるために、時間を使おう。
どこへ行くかは、明日の風と、その時の気分に任せればいい。 ちょうど、あのフレンチブルドッグにリードを引かれるままに散歩を楽しむように。
満員電車に乗り込む私の背中を、閉まりかけたドアが押す。 その衝撃さえも、今の私には「いってらっしゃい」という背中へのタッチのように感じられた。