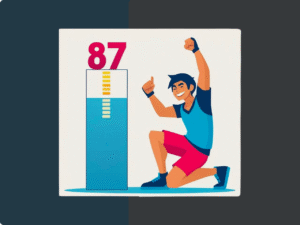学校はクラスの縛りが強すぎる。不登校だった自分が学校の嫌いなところとして思うものの一つだ。
「うち(のクラス)はうち、よそ(のクラス)はよそ」、そしてクラスのリーダーは担任の先生。学校では学年によってそれぞれ独立した集団「クラス」を形成する。授業やイベントごと、もっと言えば生徒の管理をするにはとても便利であり必要な仕組みになっているのだろう。もちろんそれは承知している。だけど、それによる弊害もある気がしていて、いじめはその一つな気がしている。
一つのクラスは大体数十人の学生と一人の「担任」と呼ばれる大人で構成されている。学生の役目は勉強をすること。勉強をするだけなら「授業をする側」と「授業を受ける側」がいれば成り立つから最低2人いれば成り立つ。つまり、同じクラスに属する学生数十人は役目を果たすのに互いが協力する必要は全くない。同じ空間にいるだけでそれぞれが個別に独立して役割を果たしている。じゃあ、クラスの学生同士が関わることはないのかというと、そういうわけでもない。お互いに気が合う者同士が集まり「友達」という関係をもってクラス内にそれぞれが小さなコロニーを形成する。この友達同士で勉強が行われる授業時間以外は「自分の席」という縛りを離れ時間を共に過ごしている。クラスの中には気の合う相手を見つけられずに孤独になるものも出てくる。そういった個体が時折いじめの対象となる。「あいつ変なやつだよな」、その言葉に対して「確かに」と共感の言葉が発せられ、一つの集団の中に一つ攻撃対象の的ができる。一つの集団に対してある共通の的(目的、共感)ができると、その集団に結束力と安心感生まれる。スポーツや戦争なんかも共通の敵がいるから、チームとしての結束力や安心感生まれるのと同じだ。
さて、もしいじめを防ごうと思った時どうするのがいいのだろうか。私は、孤立してしまった子供を別のクラスに移してしまえばいいと思う。合わない人間(環境)とはどうやっても合わない。ならば自分で気が合う奴を見つけにいけばいい。
しかし、クラスのリーダー「担任」はそうは考えない。「いじめる奴を更生させて、クラスみんなが仲良くできるように努めよう。」そう考えてしまうのだ。仮にいじめっこといじめられっ子が距離を取ろうとしたとしても、無理やり引き合わせようとすれば関係は悪化するだけだ。そうなればいじめられっ子は逃げ場を探し始める。探すべきは逃げ場じゃなくて自分に合う環境のはずだ。大人がクラスにこだわるせいで、いじめられっ子はクラス(学校)にいくか、行かないかの選択肢しか取れなくなる。身を守るならクラスに行かないのは正しいだろう。だけど、その場所は「逃げ道」として選んでいるわけだから自己肯定感も失われていく。
社会はもっと自由だ。社会不適合ってのは目の前の社会が自分に合っていないだけ。この地球上には人間の数だけ社会がある。自分に合う社会だってきっとある。というより、自分がどこの社会にも合わない唯一の存在なのだという方が難しい。とすれば、自分を否定する理由がどこにある。
教室というガラスの檻、その外に広がる無限の世界
「学校」という言葉を聞くだけで、胸の奥が少しだけきしむような感覚を覚えることがある。 私はもう大人だ。社会的には自立し、自由な時間を過ごしているはずだが、それでもふとした瞬間にあの独特の空気――チョークの粉っぽい匂いと、行き場のない閉塞感――を思い出す。
学校に行かなかった(いわゆる不登校児だった)私は。 なぜ学校が嫌いだったのか。大人になった今、ふと冷静に分析してみたくなった。私は勉強が嫌いだったわけではない。先生個人を憎んでいたわけでもない。漠然とした拒絶感に苛まれていた。その要素の一つに「クラス」というあまりにも強固で、理不尽なシステムがあった。そこに気がついた瞬間から、「いじめ」という極めて複雑な、人間関係の病理とも言えるものの原因を解析してみることにした。
学校という場所は、恐ろしいほど「枠」にこだわっている。 「うちはうち、よそはよそ」。家庭でよく聞かれるこの言葉は、学校においては「1組は1組、2組は2組」という不可侵の領域分けとして機能する。 学年ごとに独立した集団が形成され、さらにその中は数十人の生徒と、一人の「担任」という名のリーダーによって統率される「クラス」へと細分化される。
もちろん、管理する側にとってこれほど便利な仕組みはないだろう。授業の時間割を組み、行事を運営し、生徒の出欠や成績を一元管理するには、この区分けは極めて合理的だ。もちろんそれは承知している。けれど、管理の利便性を追求したそのシステムが、中にいる人間――特に未熟な精神を持った子どもたち――にどのような作用をもたらすかについて、学校という組織はあまりにも無自覚な気がする。そして、そのシステムの構造的欠陥こそが、「いじめ」という病理を生み出す原因になっているのではないのか。
冷静に考えてみれば、学校における学生の本来の役割とは「勉強をすること」だ。極論を言えば、知識を授ける「教える側」と、知識を受け取る「教わる側」の最低二人がいれば、教育という営みは成立する。 同じ教室に詰め込まれた数十人の生徒たちが、互いに協力し合わなければ因数分解が解けないわけではないし、隣の席の人間と仲良くしなければ歴史の年号を覚えられないわけでもない。機能的な側面だけで見れば、同じクラスに属する生徒たちは、たまたま同じ空間、同じ時間に居合わせただけの、独立した個の集合体にすぎないはずだ。
しかし、現実はそうドライではない。 人間は社会的動物だ。特に思春期の不安定な自我は、帰属すべき場所、安心できる「巣」を渇望する。 数十人が一つの箱に閉じ込められ、長い時間を共有することを強制された時、そこには必然的に力学が生まれる。お互いに気が合う者同士が引かれ合い、クラスという大きな枠組みの中に、さらに小さな「友達」というコロニーを形成する。授業中という「個」の時間から解放された休み時間、彼らはそのコロニーの中で安息を得る。
問題は、そのコロニー形成の過程で、どこにも属せない、あるいは「異質」と見なされる個体が現れた時だ。 「あいつ、なんか変だよな」 誰かが発したその何気ない一言は、水面に落ちた一滴のインクのように、瞬く間に集団の空気を染め上げていく。「確かに」「言えてる」という共感の言葉が積み重なるにつれ、その「変なやつ」は単なるクラスメートから、「攻撃対象」へと変貌する。
残酷な真実だが、一つの集団の中に共通の「的」ができると、その集団の結束力は飛躍的に高まる。 スポーツのチームが対戦相手に勝つために団結するように、あるいは戦時下の国民が敵国という脅威を前に手を取り合うように、教室という閉鎖空間においても「共通の敵」は、集団に安心感と連帯感をもたらすための生贄として機能してしまうのだ。いじめは、個人の性格の良し悪しだけで起こるのではない。逃げ場のない「クラス」という箱の中で、集団が安定を保とうとする際のエラー、あるいは悲しい防衛本能として発生する構造的な現象でもあるのだ。
では、この構造的ないじめを防ぐにはどうすればいいのか。 私の答えはシンプルだ。物理的に距離を取らせればいい。 孤立してしまった子、いじめの標的になってしまった子を、別のクラス、あるいは別の環境へ即座に移してしまえばいいのだ。 人間には相性がある。どうやっても合わない人間、どうやっても馴染めない環境というのは存在する。それはどちらが良い悪いという話ではなく、パズルのピースが噛み合わないのと同じ、ただの事実だ。合わないなら、合う場所、合う相手を自分で探しに行けばいい。社会に出れば当たり前のその理屈が、学校では通用しない。
ここで立ちはだかるのが、クラスのリーダーである「担任」の存在だ。 多くの教師は、善意と使命感に基づき、こう考えてしまう。 「いじめる生徒を指導して更生させよう」 「話し合って、クラスみんなが仲良くできるように努めよう」
これは美しい理想論だが、渦中の人間にとっては地獄への招待状に等しい。 水と油のように反発し合っている人間同士を、無理やり混ぜ合わせようとすればどうなるか。関係は悪化し、憎悪はより陰湿なものへと潜り込む。いじめっ子にとっても、いじめられっ子にとっても、その空間は苦痛以外の何物でもなくなる。
この時、いじめられている側の子どもが追い詰められる最大の要因は、「選択肢の欠如」だ。 大人たちが「クラス」という枠組みに固執するせいで、子どもに残された選択肢は極めて残酷な二択に絞られる。 「地獄のような教室に行って耐えるか」 「学校に行かない(不登校になる)か」
身を守るための生物的な判断として、「行かない」を選ぶのは正しい。賢明な判断だ。しかし、この選択は「より自分に合った環境への移動(ポジティブな選択)」ではなく、「ここから逃げ出す(ネガティブな選択)」として本人に突き刺さる。 「自分は逃げたんだ」 「みんなができていることが、自分にはできなかった」 逃げ場として自宅を選んだとしても、その安息の地には常に罪悪感と、削り取られていく自己肯定感が影を落とす。未成年という限られた権利と環境の中では、教室という檻から出ることは、すなわち「社会からの脱落」を意味するかのような錯覚を植え付けられてしまうのだ。
けれど、私は今、かつての私と同じように苦しんでいる君たちに伝えたい。 社会は、学校よりもずっと、ずっと自由だ。 「社会不適合」なんて言葉に怯える必要はない。その言葉は、たまたま目の前に用意された、たった一つの小さな社会(クラス)の規格に、君の形が合わなかったというだけのことだ。君が悪いわけでも、君が歪んでいるわけでもない。ただ、箱の形が合わなかっただけなのだ。
この地球上には数十億の人間がいて、無数のコミュニティがあり、数えきれないほどの「社会」が存在している。 趣味の合う仲間が集まる社会、静けさを愛する人々の社会、特定の技術を持った職人たちの社会、ネットの海の向こうにある顔の見えない社会。 これほど広大な世界の中で、自分がどこの社会にも、誰一人とも合わない「唯一無二の孤独な存在」であると証明することの方が、むしろ難しいとは思わないか? 必ずあるのだ。君が呼吸をしやすく、君の言葉が通じ、君の価値観を笑わない場所が。
今、君が感じている苦しみは、君という魚が、たまたま砂漠の真ん中に置かれた水槽に放り込まれてしまった苦しみかもしれない。周りはサボテンばかりで、君の話す「海」の話なんて誰も理解してくれないかもしれない。でも、それは君が間違っているからではない。場所が違うだけだ。
ただ、悔しいことに、今の君にはその「場所」を自分の足で選び、移動するための権利や手段が制限されている。未成年という立場は、守られていると同時に、縛られてもいる。経済力もなく、法律上の制約もあり、今すぐ海へ飛び出すことは難しいかもしれない。
だからこそ、どうか今は、自分を殺さないでほしい。 自分を歪めてまで、その狭い水槽の形に合わせようとしないでほしい。 「学校に行かない」という選択を、恥じる必要なんてない。それは君が、君自身の魂を守るために行った、尊い防衛行動なのだから。
合わない環境で傷つき続ける必要なんてない。 大人になれば、君は今以上の権利を手にする。移動の自由、契約の自由、職業選択の自由。それらはすべて、君が「自分に合う世界」を見つけに行くための翼だ。 その翼を使える日が来るまで、どうか生き延びてほしい。 教室の窓から見える空だけが、世界の全てではない。その窓枠の外側には、君が想像するよりも遥かに優しく、広く、面白い世界が、そして今までの数倍の時間が、君の到着を静かに待っているのだから。やり直しをしてる大人だってたくさんいる世界だ、多少の遅れは致命傷にはなり得ない。