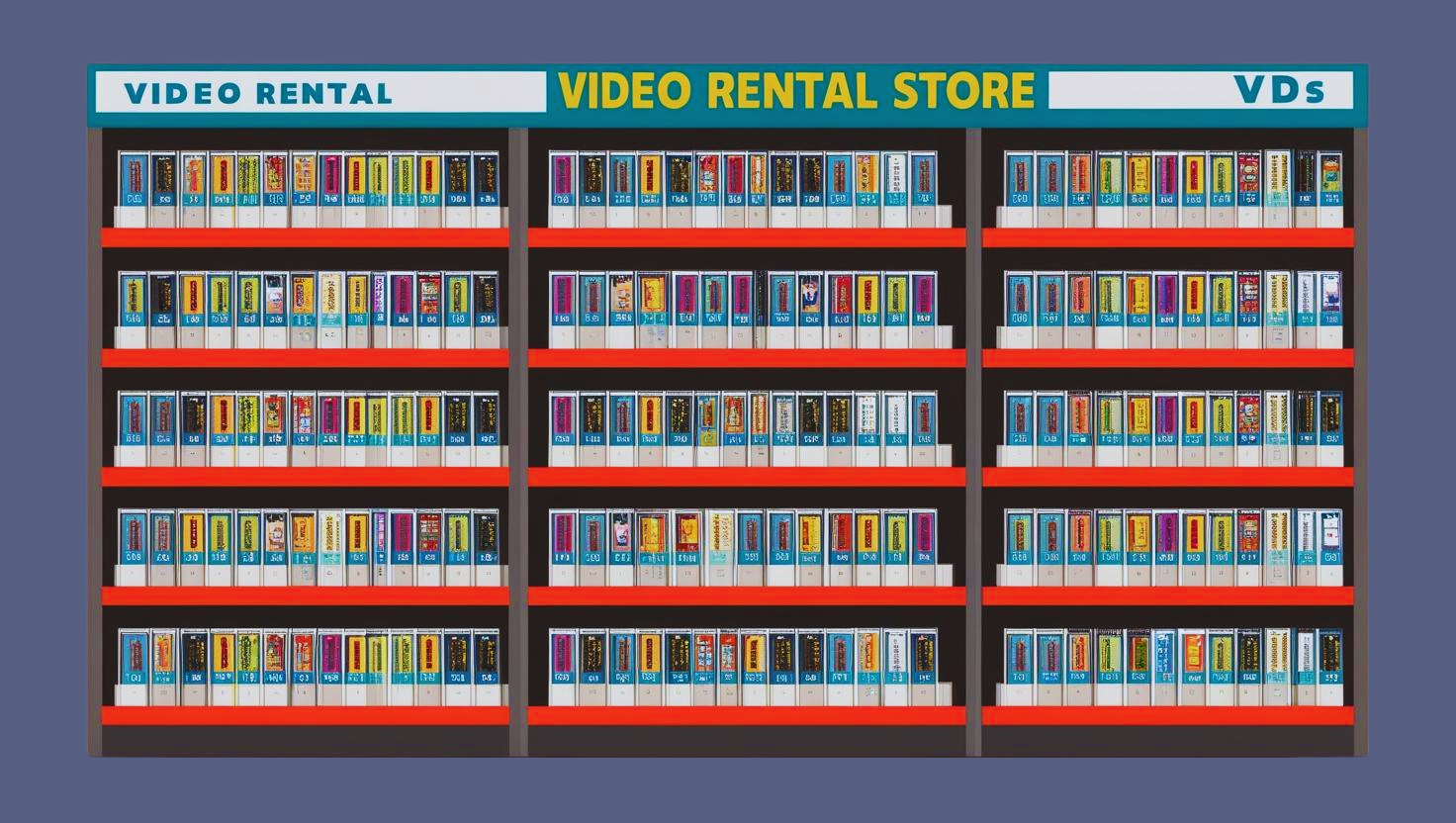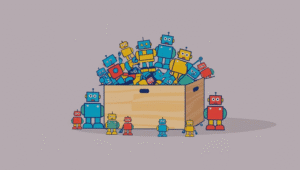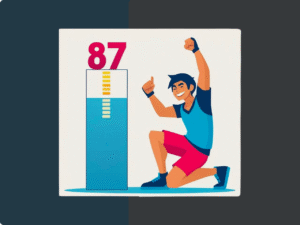最近、あえてレンタルDVDを借りにいくことにハマっている私。動画配信サイトのサブスクリプションがたくさんあるこの時代にあえて借りにいく。定額で見放題だしスマホがあればどこでもみられる、そんな便利から目を逸らしあえて不便に走るのだ。
一度に3枚までと枚数の制限を設け新作のレンタル料に頭を抱え葛藤する。レンタル後はわざわざ店舗まで赴きDVDを返しにいかなきゃいけない。だけどその不便と手間暇が愛おしい。借りたDVDをどの順番で観ようかなとか、返しにいくついでにもう一回借りて帰っちゃおうかなとか、そういう小さなワクワクは手間暇があってこそ生まれるのだ。
観たい放題もいいけど、選択肢が多すぎると何にしようか迷いすぎてそれだけで疲れちゃう。選択肢が多すぎて逆に観たいものがなくなってしまうという矛盾したような現象も起こってしまうのはそのせいだ。いつでも観れるということで、あえて鑑賞会を設ける機会もなくなった。一つの作品を見るのにわざわざポップコーンとコーラを用意して部屋を薄暗くしてみるなんてことはもうしない。ソファーで横になりながら暇つぶし程度に見るような、そんな感覚で見ることの方が多いくらいに。
だからこそ、たまに不便を味わうのだ。不便の中の手間暇に隠れたワクワクを思い出し、便利という感覚を再認識できる。
とはいえ、やっぱりサブスクでの見放題は便利だ。レンタルDVDでも、たまに自分で借りてきたにもかかわらず見るのがめんどくさくなる時もあるし。まあ観てないままの映画を返しにいく時の勿体無い感じもまた一興。
:『不便という名のチケット』
ドアが開くと同時に、どこか懐かしい匂いが鼻腔をくすぐった。古びた紙とインク、そしてわずかに漂う埃の混じった匂い。それは、かつて私の青春時代の週末を彩っていた「レンタルビデオ店」特有の空気そのものだった。
私は今、時代に逆行している。 ポケットに入っているスマートフォンを取り出せば、そこには無限の世界が広がっている。月額千円程度で、映画もドラマもアニメも見放題。指先一つで世界中のコンテンツにアクセスでき、通勤電車の中でも、入浴中でも、ベッドの中でも、好きな時に好きな場所で続きが見られる。そんな魔法のような利便性が当たり前になったこの令和の時代に、私はあえて、この薄暗い店舗に足を運ぶことにハマっていた。
「いらっしゃいませ」
店員の気の抜けた声が響く。蛍光灯に照らされた棚には、プラスチックのケースが整然と並んでいる。私はその光景を見るだけで、奇妙な高揚感を覚えるのだ。
あえて、借りにいく。 定額で見放題の「便利」から目を逸らし、あえて「不便」という贅沢を買うために。
私は黒い手提げ袋を握りしめ、新作コーナーの前に立った。 そこには厳しいルールが存在する。私が自分自身に課した「一度に借りられるのは三枚まで」という鉄の掟だ。 サブスクリプションの世界なら、気になったものを片っ端からマイリストに入れればいい。しかし、ここではそうはいかない。物理的な限界と、財布への打撃があるからだ。
「新作四百円……準新作なら百円……」
私はケースを手に取り、裏面のあらすじを睨みつける。この一本に四百円の価値はあるのか。あるいは、旧作コーナーで名作を掘り起こすべきか。 眉間に皺を寄せ、棚の前を行ったり来たりする。傍から見れば優柔不断な客に過ぎないだろうが、私の頭の中では壮絶な取捨選択の会議が行われているのだ。この葛藤こそが、映画体験のプロローグなのだと私は信じている。
「これだ」と決めた三枚をカウンターへ持っていく時の、少しの緊張感と達成感。 財布から小銭を取り出し、レシートと一緒に会員証を受け取る。 「返却期限は一週間後となっております」 その言葉には、拘束力という名の重みがある。期限があるからこそ、私たちは時間を意識する。いつでも見られるという安心感は、時として「いつまでも観ない」という怠惰を生むからだ。
店を出ると、夜風が少し冷たかった。 手提げ袋の中で、三枚のDVDケースがカチャカチャと音を立ててぶつかり合う。そのチープなプラスチックの音が、私には心地よい音楽のように聞こえた。 「さて、どれから観ようか」 帰り道を歩きながら、私は袋の中身を思い浮かべる。一番楽しみにしていた新作を最初に観るか、あるいは準新作を前菜として楽しむか。それとも、とっておきの新作は週末の夜のために温存しておくべきか。 そんな小さなワクワクが、アスファルトを踏みしめる足取りを軽くさせる。この、家に帰るまでの「移動時間」という無駄な空白こそが、期待感を醸成するためのスパイスなのだ。
かつて、サブスクリプションの海に溺れていた頃の私は、逆説的な孤独を感じていた。 画面には数千、数万というタイトルが並んでいる。アクション、恋愛、ホラー、ドキュメンタリー。おすすめ機能が次々と「あなたへの一作」を提示してくる。 しかし、選択肢が多すぎることは、時に不幸だ。 夕食後の貴重な一時間を、ただサムネイルをスクロールするためだけに費やしてしまう。「これも面白そう、でもこっちの方が評価が高い」。迷っているうちに脳が疲れ果て、結局何も観ずにYouTubeで短尺の動画を流し見して寝てしまう。 あるいは、映画を再生したとしても、冒頭の十分がつまらなければすぐに停止ボタンを押して次を探す。映画が「作品」ではなく、単なる「消費データ」に成り下がっていた。
「映画鑑賞」という儀式は、もっと神聖なものだったはずだ。
アパートに帰り着いた私は、買ってきたばかりのポップコーンを皿に開け、冷蔵庫からコーラを取り出した。 部屋の照明を落とし、間接照明だけの薄暗い空間を作る。 これこそが、レンタルDVDにおける作法だ。 ソファーに寝転がりながらスマホ片手に流し見をするのとは訳が違う。私は今から、四百円と、借りに行く手間と、返しに行く労力を支払ったこの作品と対峙するのだ。その対価に見合うだけの集中力を注がなければならない。
ディスクをトレイに乗せる。「ウィーン」という駆動音が鳴り、読み込みが始まる。 画面に現れる「無断複製禁止」の警告すら、今では愛おしい。飛ばせない予告編に少しイライラするのも含めて、映画館の上映開始を待つ時間に似ている。 そして本編が始まる。 私はポップコーンを頬張りながら、画面に没入する。スマホの通知など見向きもしない。不便を乗り越えて手に入れたこの二時間は、誰にも邪魔させない私だけのサンクチュアリだ。
一本見終わった後の余韻もまた、格別だった。 エンドロールが終わっても、すぐに次の作品が自動再生されることはない。ディスクを取り出し、ケースにしまうという物理的な動作が、物語への別れと感謝の儀式となる。 「面白かったな……」 パッケージの裏面をもう一度眺める。監督の名前を確認し、印象に残ったシーンを反芻する。手元に「モノ」があることで、その体験は記憶に深く刻まれる気がした。
もちろん、不便は不便だ。 「ああ、今日が返却日か……」 雨が降る休日の朝、玄関に置かれた手提げ袋を見て溜息をつくこともある。 サブスクなら、クリック一つで解約も視聴終了もできるのに、レンタルDVDはわざわざあの店まで足を運び、返却ボックスに入れなければならない。 濡れた傘を畳み、水たまりを避けながら店に向かう道中、「なんでこんな面倒なことをしているんだろう」と我に返りそうになる瞬間がないわけではない。
しかし、その面倒くささの中にこそ、日常の「手触り」があるのだと思う。 店に向かう道すがら、雨に濡れた紫陽花が綺麗だと気づくこと。 返却ボックスに「ガコン」とケースを放り込んだ時の、肩の荷が下りたような開放感。 そして、「せっかく来たんだから」と、またふらふらと棚の間を彷徨い始め、思いがけず懐かしい映画の背表紙を見つけた時のときめき。 「あ、これ昔好きだったな」 そうしてまた、予定になかった三枚を手に取ってしまう。 この循環。効率化された社会では「無駄」と切り捨てられるこのサイクルの中に、予期せぬ出会いや、小さな喜びが隠されている。
便利なものは素晴らしい。それは間違いない。 疲れている時にベッドから一歩も動かずに映画が見られるサブスクの恩恵を、私は否定しない。むしろ、その便利さを知っているからこそ、あえて選ぶ不便さが輝くのだ。 毎日がフルコースでは胃がもたれるように、毎日が超効率化されたデジタルライフでは心が乾いてしまう。 たまに味わう不便は、心のストレッチのようなものだ。
ある時、三枚借りたうちの一枚を、忙しさにかまけて観ないまま返却日を迎えてしまったことがあった。 袋から取り出したディスクは、一度もプレイヤーに入ることなく、ただ私の部屋の空気を吸っただけで店に帰ることになる。 「四百円、無駄にしちゃったな」 店に向かいながら、私は苦笑する。 だが、その「勿体なさ」すらも、どこか憎めない感情として胸に残る。観なかった映画のタイトルは、逆に強く記憶に残る。「次は絶対観てやるからな」という奇妙な執着と共に。 データとして処理され、視聴履歴にすら残らない「未再生」とは重みが違うのだ。
私は返却ボックスに袋を入れる。 空になった手でポケットを探り、スマホを取り出すのではなく、夜空を見上げた。 街の明かりが雲に反射している。 次はどんな世界を借りて帰ろうか。 そう考える私の足取りは、来る時よりも少しだけ弾んでいた。 便利さが削ぎ落としてしまった「手間暇」という愛おしい時間を、私はこれからも大切に抱きしめていこうと思う。