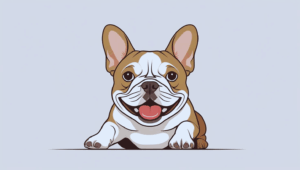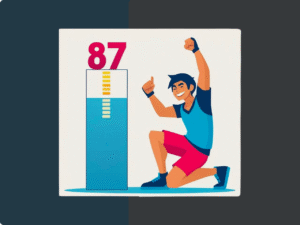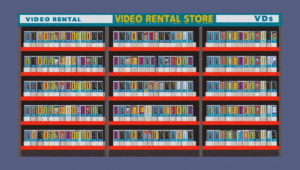第一章:街の輝き、心の翳り
「お先に失礼します。」
会社を出て家に帰るためにいつもの道を通り最寄りの駅へと向かう。しかし、今日だけは同じ道でもいつもとは違う。それは終業時刻が近づくにつれ、まるで生き物のようにざわめき出し、空気そのものがきらめきを増していた。巨大なツリー、街路樹に巻き付けられた無数のLED、ビルの壁面を飾るプロジェクションマッピング。眩しいほどに奔流するそれらの光は、今年の冬の寒さを忘れさせるほどの熱を帯び、視界いっぱいに広がっている。耳に届くのは、耳馴染みのある甘いラブソングと、弾むような人々の笑い声。
今宵はクリスマスイブ。冬一番のイベントだ。恋人たちは寄り添って写真を撮り、幼い子供を連れた夫婦は両手に抱えきれないほどの荷物と夢を抱えて通り過ぎる。どの顔も満たされ、安心しきっている。彼らの周りだけ、世界の時間軸から切り離された、温室のような空間が広がっているようだった。
人々はそれぞれの大切な人と過ごすのだろう。それは家族、恋人、あるいは気心の知れた友人たち。
私自身、自分から積極的に誰かを誘った訳でも、お付き合いしている人がいる訳でもないため俗にいう”クリぼっち”なるものに相成りました。
とはいえ私だって、本当はその「人々」の一員でありたかった。
別に、一人でクリスマスを過ごすことが、特別に変だというわけじゃない。仕事が忙しかったり、単に興味がなかったり、様々な理由で一人を選ぶ人はいる。この状況に陥っているのが、選んだ孤独なのか、それとも選ばれなかったが故の孤独なのか。どちらにしろ、眩しいほどに輝く空間を私一人、無防味に歩いていくこの光景はただ惨めなだけだった。
防寒具で身を固めているというのに、心の奥底から湧き上がってくる冷気が、足元からじわりと全身を凍らせていくのを感じた。街全体が「あなたは誰といるべきか」を問うているようで、その問いに答えられない自分を、ひたすら責めているような錯覚に陥る。
通りを一つ曲がると、さらに人の密度は増し、歩調は自然と遅くなった。立ち並ぶカフェやレストランの窓からは、暖色系の光と共に、シャンパンの泡や、楽しげな会話の断片が漏れ聞こえてくる。私と店の窓ガラスを隔てているのは、わずか数センチの空間にすぎないのに、その向こう側にある「幸せ」は、地球の裏側にあるくらい遠く、手の届かないものに感じられた。
第二章:煩わしさの波と自己嫌悪
大通りに出ると、イルミネーションの輝きは最高潮に達した。
「煩わしい」
あまりにも明るく、あまりにも鮮やかで、私の目に映るすべての色彩が、白く焼き尽くされていくようだった。本来であれば、この光の芸術を素直に「綺麗だ」と楽しむべき特別な一日なのに、私はそれを拒否していた。私を照し出す光は、この街でただ一人立ち尽くしている私の孤独を嘲笑うかのように強調している。「会えない時間が愛を育む」、だとか、「来年も再来年も、君の隣で」、だとか、耳を覆いたくなるほど大音量で流れるラブソングも、今はただの雑音だ。
隣に立つ男性が、愛しそうに彼女の肩を抱いている。その彼女の幸せそうな笑顔。その一瞬の光景が、私の中に潜む、他人へのねじれた感情を引きずり出す。嫉妬。ああ、これこそが嫉妬だ。自分にはないものを、他者がたやすく持っていることに対する、醜い羨望。
「別に、羨ましいわけじゃない」と、頭の片隅で理性で抵抗しようとするが「自分も誰かの隣にいたかった」という拗ねた本音に苛まれる。
嫉妬はすぐに、自虐的感情として自分自身に向けられた。
なぜ、私はこの夜を一人で過ごしているのか。誰にも必要とされない人間だからだろうか。愛想が悪いからか。この一年、誰かを大切にすることを怠った罰なのだろうか。
他人への嫉妬と一緒に、誰かと一緒に過ごせないという惨めさが混ざり、小さな自己嫌悪が芽生える。
街は隅々まで幸福で満たされている。それはそれで喜ばしいことじゃないか、他人が幸せならそれでいい。他人の幸せを拝められるだけで、十分だ。
一歩足を止める。きらびやかなツリーの光によって、私は自分の心の底に溜まった泥のような感情は、クリアに目の前に晒されているようだった。
第三章:サンタクロースの献身的な心
自己嫌悪の渦中で、ふと、ある人物のことが頭をよぎった。サンタクロースだ。
サンタさんは、子供たちにプレゼントを配る。配ることで、子供たちの喜びを、親たちの安堵を、街の幸福を、一身に引き受ける。
サンタさん自身の「幸せ」とは一体何なのだろうか。彼は、見返りを求めない。自分の存在を主張することもなく、ただひたすらに、他者の幸福のために行動する。そして、おそらく彼は、子供たちの笑顔や、その家庭に訪れる平和な瞬間にこそ、最高の喜びを感じているのだろう。
他人の幸せを自分の幸せにできちゃうなんて。
彼は、人としての「器」が、私とは比較にならないほど大きい。献身的で、利他的で、無償の愛に満ちている。そして私も毎年その愛を受け取っていた。
もし、私がサンタさんが持つその「心の器」を少しでも持てたとしたら、この夜の景色はどのように変わるだろうか。
あのカップルの幸せを、心の底から「よかったね」と祝福できる自分。あの家族の暖かさを、まるで自分のことのように温かく感じられる自分。もしそうできたら、一人で歩くこの街の中の幸せに、私は包まれて歩くことができるのだろう。
イルミネーションの光は、もはや私を嘲笑う光ではなく、誰かの幸福の灯火として、私自身の心を照らす光になる。ラブソングの旋律は、私の孤独を煽るものではなく、ただ純粋な愛を歌う美しい音楽として、私を癒すだろう。
私に、まだサンタさんからのプレゼントをもらえる権利が、子供のように少しでも残っているのならば、物質的なものは何もいらない。サンタさんが持つ、その利他的で献身的な心の器を、ほんの少しでいいから、もらえたらと願う。私の自己嫌悪を、この惨めさを、溶かし去ってくれるような、温かい心を。
そんなことをぼんやりと考えながら、私は大通りの信号で立ち止まった。視線は自然と、赤信号で横断を待つ、雑多な人々の群れへと向く。
交差点を挟んだ反対側、老舗のおもちゃ屋だろうか、そこから家族が出てくるのが見えた。父親が、わめいて駄々をこねる小さな子供を抱え上げ、母親がなだめようとしている。
第四章:景色の一部としての愛おしさ
子供の泣き声は、街の喧騒とラブソングの音量を貫き、私の耳に届いた。
「もう!なんでないの!サンタさんにもらったやつがいい!」
聞こえる範囲の情報から推測するに、どうやら欲しかった、あるいはサンタさんにお願いしたはずのおもちゃが手に入らなかったようだ。子供の全身から発せられる「不満」と「怒り」のエネルギーは凄まじい。父親も母親も、この特別な夜に、子供の最悪の感情をどう処理していいか戸惑っているのが見て取れた。
子供からすれば、確かに今日は最悪な日だろう。期待していたものが手に入らない失望、それがクリスマスという特別な日に起きたことへの怒り。その子供の気持ちは、理不尽ではあるが、素直で純粋な絶望だ。
その光景を、街の雑踏の一部として、まるで遠い舞台を見ているかのように見ている自分に気づく。私は、そこには入れない。声をかけることも、手伝うこともできない。ただ、交差点を挟んで見つめる、傍観者だ。
しかし、その傍観者の視点から見るその家族の姿は、どういうわけか、私の胸に刺さっていた棘を少しだけ緩ませた。
私にとって、クリスマスは「寂しさ」と「自己嫌悪」という、内的な地獄だった。 あのカップルにとって、クリスマスは「愛」と「満たされた時間」という、幸福の極致だった。 あの子供にとって、クリスマスは「期待と失望」という、世界が終わるかのような悲劇だった。
一つの同じイベントが、その場にいる人間それぞれの、異なる、極端な感情を引き出している。
「欲しかったおもちゃが手に入らなかった、最悪のクリスマス」。
でも、それを街の風景の一部として見ている私からすれば、それもまた、クリスマスならではの景色なのかな、と思えたのだ。
完璧な幸せだけが、クリスマスじゃない。完璧な孤独だけが、クリスマスじゃない。
あの子供の泣き声も、その子供を抱える親の困惑した表情も、遠目には、ただの愛おしい「クリスマスの瞬間」に見える。彼らは今、幸せの絶頂にいるわけではないかもしれない。むしろ、トラブルの渦中にある。それでも、そのトラブルを含めて、彼らは「家族」として、この特別な夜を共有している。
その瞬間の彼らには、私が嫉妬していた眩しい光も、煩わしいラブソングも、届いていないだろう。彼らの世界は、子供の泣き声とその対応で満たされている。
彼らの風景を見たことで、私の感情の焦点が、自分自身の内側から、外側の世界へと、ほんの少しだけ移動した。
ああ、私はこの夜、ずっと自分の惨めさ、自分の寂しさ、自分の持っていないものばかりを見ていた。だから、眩しい光を浴びるたびに、心が痛んだのだ。
だが、駄々をこねる子供と、それに手を焼く家族の光景は、クリスマスという巨大な祝祭の風景の中に、私自身の孤独や惨めさと同じくらい、不完全で、人間臭い感情も含まれていることを教えてくれた。
私の寂しさが、この街の風景をより立体的にしているのではないか。私の自己嫌悪が、誰かの幸せをより際立たせているのではないか。
サンタの利他的な心はまだ手に入らないけれど、少なくとも、この街の美しさ、醜さ、楽しさ、悲しさを、すべて客観的に受け入れる「視点」は与えられた気がした。それは、ささやかな、けれどかけがえのない贈り物だった。
信号が青に変わり、私は交差点を渡った。さっきまで見ていた家族は、角を曲がって見えなくなった。彼らのドラマは、まだ続いているだろう。
輝くイルミネーションも、幸せそうなカップルも、一人自己嫌悪に陥っている奴も、駄々をこねる子供も、そして、その子供をなだめる親の姿も。全部ひっくるめて、クリスマスなんだろう。
そう思うと、胸の中にあった張り詰めた糸が、ふっと緩んだのを感じた。
私の寂しさは消えていない。この夜を一人で終える事実は変わらない。しかし、その寂しさが、もはや私を責め苛むものではなくなった。
「この寂しさもまた一興かな」
ほんのわずかな諦めと、受け入れの感情が、私の中に残った。
この孤独な感情もまた、クリスマスの持つ多面性の一つである。それはまるでツリーを飾るオーナメントのような。
少し心が暖かくなったのを感じて、私は大通りを抜け、人通りの少ない裏通りへと進路を変えた。街の喧騒は遠ざかり、代わりに聞こえてくるのは、自分の足音だけだ。
裏道の街灯は、大通りのイルミネーションほど眩しくはない。ぼんやりとした暖色系の光が、アスファルトを静かに照らしている。この静けさが、今の私には心地よかった。
サンタの心はもらえなかったけれど、私は今、誰にも邪魔されない、自分だけの静かなクリスマスの夜を歩いている。そして、この孤独な道の先に、来年、誰かの幸せを心から喜べるような自分になれたら、きっと、その時こそ、最高のプレゼントを受け取ったことになるのだろう。
そんな未来への静かな願いを胸に、私は家路を急いだ。