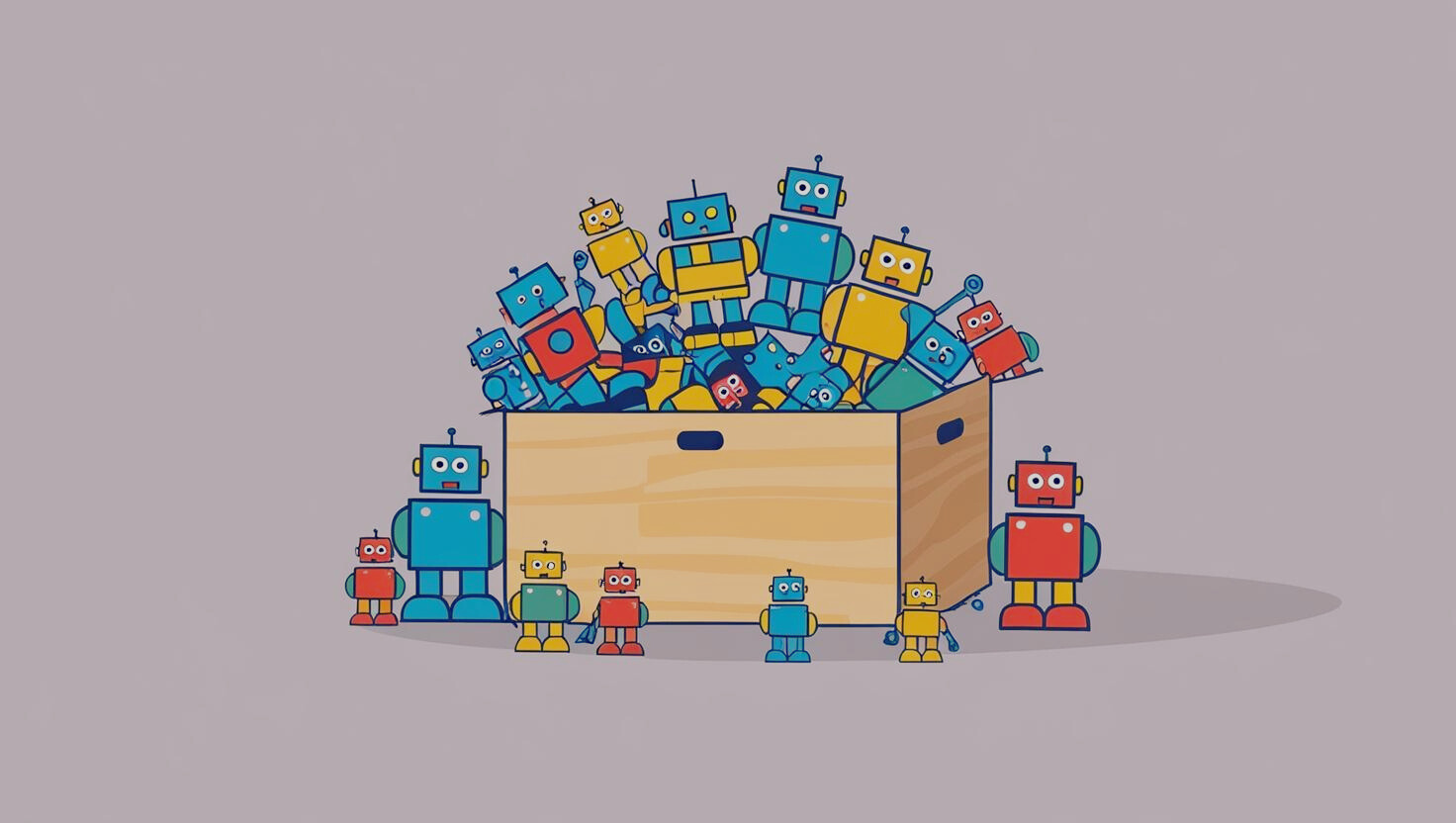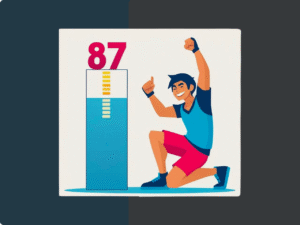子供の頃は周りの目を気にして遊ぶことはなかった。小学生に上がる前、自分はロボットのおもちゃで遊ぶのが大好きだった。ただ遊ぶのではなく、戦いの経緯やそれぞれの配役など設定を細かく決めた上で遊ぶのが好きだった。まるでシーンを切り替えるかのように何度もロボットを持ち変え、役ごとに声色も変えた。監督、声優、全て私の完全妄想劇場、それが小さかった頃の私の大好きな遊び。なんの疑問もなくただ純粋に好きだった。
小学生に上がった頃から、私はその純粋さを失い始めた。クラスでは携帯ゲーム機が流行。もちろん自分も母ちゃんに買ってもらうようおねだりをした。単純にクラスの流行に乗りたいと言う理由もあったがそれ以外の理由がもう一つあった。それはクラスの中で「おもちゃは小さい子供が遊ぶもの。小学生になったらゲームでしょ。」という風潮があったから。私は「いまだにおもちゃで遊んでいるダサいやつ」からの卒業のきっかけにしたかった。結果としてゲーム機は手に入った。同時に私はこれまで私の妄想劇場に携わってきたおもちゃたちを押し入れの奥へとしまった。
もちろんゲームをするのは大好きだ。だけど別におもちゃ遊びも飽きてしまったわけじゃない。いまだにおもちゃで遊んでいると思われることが恥ずかしかった。周りの目を気にして自分の好きなことに蓋をして、初めて「自分も君たちと同じだよ」と建前を取り繕ったのだ。その頻度は年齢を重ねるたびに増えていく。自分が好きだと言えるかどうかは周りからの視線を基準にして決める。大人になって空気を読むことと本音を隠すことの区別がつかなくなってしまった。
子供の頃は大人になれば自分の好きなことを好きなだけできるようになると思っていたが、案外そうでもないみたいで。やりたいことなんて特にないなんて大人はたくさんいる。きっと1ヶ月の夏休みを与えられたとしても、時間を持て余して「こんなに休みはいらない」なんていう大人は多い。毎日遊ぶことに夢中になって一瞬の夏休みを過ごせるっていうのはすごいことだ。好きなことに蓋をしていると好きなことがわからなくなる。自分の中から本当の純粋さが離れていくことで大人になっていくとするのならば、大人になるということはとても寂しいことのような気がする。きっと今でもその純粋さは求めている。懐かしく思うことで心が落ち着くのはその証拠だろう。もし、大人になった今、引き出しの中からおもちゃを取り出し、昔のように役の配置から考えもう一度、おもちゃ遊びをしようとするなら、おもちゃたちは自分の勝手でおもちゃたちを押し入れに閉じ込めた自分を歓迎してくれるだろうか。それとも、おかえりと言って歓迎してくれるだろうか。そんなことを考えながらまるで小さい頃の友達のように懐かしさを馳せてみる。
妄想劇場の観客席
金曜日の夜九時。最寄り駅の改札を抜け、コンビニで発泡酒と味の濃いスナック菓子を買う。スーツのネクタイを緩めながら、僕は重い足取りでワンルームの自室へと戻った。 鍵を開け、明かりをつけると、殺風景な部屋が浮かび上がる。洗濯物が溜まったソファ、読みかけのビジネス書、そして会社用の鞄。ここにある全てが、僕が「まともな社会人」であると主張しているようで、ひどく息苦しかった。
僕は新卒で入社した会社の、一年目の社員だ。 仕事が嫌いなわけではない。ただ、毎日毎日、空気を読み、愛想笑いを浮かべ、自分の意見よりも「正解」とされる言葉を選んで口にすることに、どうしようもない疲労を感じていた。 プシュ、と缶を開ける音が静かな部屋に響く。一口飲むと、炭酸の刺激と共に、今日一日の澱(おり)のような感情が胃の腑へと落ちていく気がした。
ふと、視線が部屋の隅にある押し入れに向いた。 実家から引っ越してくるとき、母が「これ、どうするの? 捨てる?」と聞いてきた段ボール箱。中身を確認することなく、「とりあえず持っていく」と答えた箱が、奥の方に押し込まれているはずだった。
僕は吸い寄せられるように立ち上がり、押し入れの襖を開けた。 その箱は、衣装ケースの奥でひっそりと息を潜めていた。ガムテープを剥がす音が、妙に大きく響く。 蓋を開けた瞬間、懐かしい匂いがした。埃と、プラスチックと、それから、あの頃の僕の熱気が入り混じったような匂い。 そこに眠っていたのは、数々のロボットのおもちゃたちだった。
僕がまだ、ランドセルを背負う前のことだ。 僕は、このロボットたちで遊ぶのが大好きだった。ただ戦わせて、ガチンガチンとぶつけ合うだけではない。僕の遊びは、もっと高尚で、緻密なものだった。 六畳の和室は、僕にとって無限の宇宙であり、荒廃した戦場であり、時には秘密基地の格納庫だった。 まず、設定を決める。こいつは正義の味方だが、過去に傷を負っていて、普段は無口だ。敵役のこいつは、実は主人公の兄貴分だったが、悪の組織に洗脳されている。そんな背景ストーリーを、ノートに書き出すわけでもなく、脳内で完璧に構築するのだ。 そして、開演のベルが鳴る。 僕は監督であり、脚本家であり、そして何より、彼らに命を吹き込む声優だった。 「くそっ、これ以上近づくな!」 主人公機を握りしめ、喉を絞って少年のような高い声を出す。 「フフフ、無駄だ。私の力を見るがいい」 即座に敵役のロボットに持ち替え、今度は腹の底から響くような低い声を出す。 右手と左手で異なる人格を操り、効果音さえも自分の口で奏でる。爆発音、ビームの音、金属が軋む音。 周囲の目など、これっぽっちも気にしていなかった。いや、気にするという概念さえ知らなかった。そこには「僕」という存在はなく、ただ物語の世界だけがあった。完全なる没頭。完全なる妄想劇場。 それは、僕が人生で初めて手にした、何にも代えがたい「世界」そのものだった。なんの疑問もなく、ただ純粋に、僕はその世界を愛していた。
その純粋さが曇り始めたのは、小学校に上がってすぐの頃だったと思う。 クラスの話題は、携帯ゲーム機一色になった。休み時間になれば、みんなで小さな画面を覗き込み、通信対戦に熱中する。 「えー、お前まだそんなおもちゃで遊んでんの?」 誰かが何気なく放ったその言葉が、僕の胸に鋭い棘のように突き刺さった。 悪意はなかったのかもしれない。けれど、その言葉は明確な線引きだった。「こちら側」と「あちら側」。ゲームで遊ぶのが小学生、おもちゃで遊ぶのは小さい子供。 僕は恐怖した。「いまだにおもちゃで遊んでいるダサいやつ」というレッテルを貼られることが、死ぬほど怖かった。
その日の夜、僕は母ちゃんにねだった。 「みんな持ってるから、僕もゲームが欲しい」 純粋にゲームがしたかったのもある。でも、それ以上に大きな理由は、そのおもちゃたちからの「卒業」を演出するためだった。 数日後、念願のゲーム機を手に入れた僕は、まるで儀式のように、それまで毎日枕元に置いていたロボットたちを段ボール箱へと詰めた。 別に飽きたわけじゃない。昨日まであんなに楽しかった妄想劇場の台本は、まだ僕の頭の中に残っていた。 けれど、僕は蓋を閉めた。 自分の「好き」という感情よりも、周りからどう見られるかという「評価」を選んだのだ。 「自分も君たちと同じだよ」 そうやって建前を取り繕うことで、僕は初めて社会という集団の中に居場所を確保した。それが、僕が大人になるための最初のステップだった。
それからは、ずっとその繰り返しだ。 中学生になれば聴く音楽を周りに合わせ、高校生になれば読む漫画や服のブランドを流行に合わせ、大学生になればサークルのノリに合わせ、そして今、社会人になって上司の顔色に合わせて生きている。 自分がそれを好きかどうかは、二の次だ。周りの視線というフィルターを通してでなければ、自分の感情さえ決められなくなってしまった。 本音を隠し、空気を読むことこそが「大人になること」だと信じて疑わなかった。
でも、どうだろう。 子供の頃、大人は自由だと思っていた。お金もあって、時間も自分で決められて、好きなことを好きなだけできる存在だと。 けれど実際になってみると、僕を含めた大人の多くは、自由を持て余しているように見える。 「やりたいことなんて特にない」と乾いた笑いを浮かべる先輩。もし一ヶ月の夏休みを与えられたら、きっと多くの大人は三日目で不安になり、「こんなに休みはいらない」と言い出すのではないだろうか。 毎日毎日、朝から晩まで遊ぶことに命を懸け、一瞬で夏休みを駆け抜けていたあの頃の僕たち。あのエネルギーは、一体どこへ消えてしまったのだろう。
好きなことに蓋をし続けていると、やがて蓋の中身が何だったのか、自分でもわからなくなる。 本当の純粋さが、体から抜け落ちていく。 もし、それを「成長」と呼ぶのなら、大人になるということは、なんて寂しくて、空虚なことなのだろう。
全力で自分の世界に注力すること。 誰になんと言われようと、汗だくになってロボットを握りしめ、声を枯らして物語を紡ぐこと。 あの「没頭」こそが、子供だけが持つことを許された、最強の武器だったのだ。そしてそれは、大人が一番躊躇し、恐れ、けれど心の奥底で最も渇望しているものなんじゃないか。
薄暗い部屋の中で、僕は箱の中から一体のロボットを取り出した。 赤いボディの、かつての主役機だ。所々の塗装が剥げ、関節が少し緩くなっている。それは僕が彼を愛し、共に戦った日々の勲章だった。 ひんやりとしたプラスチックの感触が、指先を通して記憶を呼び覚ます。
僕は彼を、自らの勝手な都合で闇の中に押し込めた。 周りに合わせるために。ダサいやつだと思われないために。保身のために、彼らを裏切ったのだ。 今さら、どの面を下げて彼らに触れているのだろう。
もし、おもちゃたちに心があるとしたら。 彼らは、十年以上の時を経て再び光の下に出された今、僕になんて言うだろうか。 『よくもあんな暗い場所に閉じ込めたな』と怒るだろうか。 『もうお前とは遊んでやらない』と背を向けるだろうか。
僕は震える手で、ロボットを床に立たせた。 フローリングの床。あの頃のような畳の匂いはない。 それでも、僕は彼を見つめた。 関節を曲げ、構えを取らせる。右手を上げ、敵を見据えるポーズ。指が覚えていた。何千回、何万回と繰り返した、あのかっこいいポーズを。
その瞬間、胸の奥がきゅっと締め付けられるような、それでいて温かいものが込み上げてきた。 ノスタルジーなんて言葉じゃ片付けられない。もっと切実で、愛おしい感覚。
ロボットは、何も言わない。 けれど、その傷だらけの赤い背中は、僕を拒絶しているようには見えなかった。 むしろ、静かにこう言っているような気がした。
『おかえり。ずっと待っていたよ』 『また、続きを始めようぜ』
僕は涙がこぼれそうになるのを堪え、小さく息を吐いた。 三千文字にも満たない僕の人生のプロットの中で、あの頃の妄想劇場ほど輝いていた章は、まだない。 今の僕には、あの頃のように声を張り上げ、全身全霊で彼らになりきることは難しいかもしれない。明日はまた仕事があるし、常識という鎧を脱ぎ捨てることは怖い。
それでも。 僕はもう一体、敵役のロボットを箱から取り出した。 黒いボディの、かつてのライバル。
「……久しぶりだな」
独り言のように呟く。声は小さく、少し震えていたけれど、それは確かに「僕」の声だった。上司に向けた声でも、同僚に合わせた声でもない、僕自身の声。 大人が失ってはいけないものは、きっとこういう時間の中に隠されている。
僕は缶ビールを横に退け、ネクタイを完全に解いた。 夜はまだ長い。 誰も見ていない、この狭い部屋の中だけなら、僕はもう一度、あの劇場の監督に戻れるかもしれない。 止まっていた時計の針を動かすように、僕は二体のロボットをゆっくりと向かい合わせた。