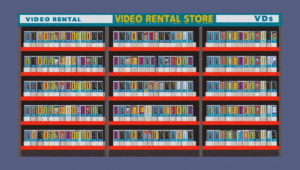多様性。みんな違ってみんないい。それぞれの個性を認めましょう。
最近ではそんな言葉が謳われるようになったと同時に、「こうあるべきだ」という言葉が規制されている。が、言葉自体には別にいいも悪いもないと思う。大事なのはその言葉をどこに向けるかだ。「〜であるべきだ」という言い方にはその人個人の願望が含まれる。だから他人に向けると押し付けがましくなる。特別な発言力があるか何か個人的な感情を持つ人でもなければ、ただの一般人に言われてもうるさいだけ。そういった言い方を向けていいのは自分自身にだけだ。
逆に自分の願望を惜しみなくぶつけられる唯一は自分自身のみだ。「こうありたい」、「こうあるべきだ」、自分の中にある理想を大義として掲げる。その大義が周りに認められなかった時、または否定された時に、どうにかして自身の大義を認めさせてやろうと思ってはいけない。絶対に他人に振りかざすな。あくまでそれは自己満足。自分がかっこいいと思っているからやっているだけ、という前提のもとにあれば他人の評価にも笑っていられるし、徹底的に理想を詰められる。迷いがない奴が強いのはそういうところからだろう。
人はそれぞれ大義を掲げてる。それが自分の掲げる大義に反するかもしれない。もしそうなら、その人とは距離を置けばいいだけの話。合わない人間とは合わないし、合う人間も絶対にいる。個性を認めようとはそれを理解すること。相手の色を無理に受け入れ寄り添おうとすることじゃない。合わなければ関わらない。冷たいように思われそうだが、私は実に平和的な考えだと思う。無理して寄り添い合う関係になんの意味がある。そんなことで寄り添ってこられるのも少し屈辱的に思える。
掲げる大義に矛盾を感じ本当にこれでいいのかと悩む時もある。そんな時は思いっきり悩めばいいと思う。解決しなそうなら開き直りながら、それでも納得がいかないならまたそいつに向き合う。なりたい自分がないっていうのは嘘だよ。「なりたい」が「なれない」に押しつぶされている。大義は自分だけが知っていればいいんだ。だから人に直接自分の大義を否定されるようなことはそんなにないはず。ならば恥ずかしがる意味はない。自分の理想に掲げる旗をぶっ差しにいけ。
:静寂の砦に旗を立てろ
本屋に立ち寄って店内をぶらついてみる。本の表紙は色とりどりの言葉に飾られている。「多様性」。「みんな違って、みんないい」。かつては教室の標語でしかなかったような言葉が、今や社会全体を覆う絶対的な正義として君臨している。それはとても優しく、耳心地が良く、だけどどこか掴みどころのない霧のようだ。
その霧の対岸で、まるで危険物のように扱われ始めている言葉がある。「こうあるべきだ」という言葉だ。
かつては美徳や規範を示す羅針盤だったはずのこの言葉は、今や「多様性を阻害する鎖」として、あるいは「他者への圧力」として、口にすることさえ憚られる空気が漂っている。柔軟性がない、古い、押し付けがましい。そんなレッテルと共に、人々はこの言葉を喉の奥に押し込んでいる。
だが、私は思うのだ。言葉そのものに善悪の色などついていない。包丁が料理人の手にあるか、暴漢の手にあるかで意味を変えるように、「こうあるべきだ」という言葉もまた、その矛先をどこに向けるかで、凶器にもなれば、人生を削り出す彫刻刀にもなる。
結局のところ、問題は「誰に向けた言葉か」という一点に尽きる。
「あなたはこうあるべきだ」 「社会はこうあるべきだ」 「普通はこうあるべきだ」
これらはすべて、他者への侵略だ。特別な権威もなければ、その人の人生に責任を持てるわけでもない一般人が、他人の領域に土足で踏み入るための言葉。そこには、発言者の個人的な願望が含まれている。「私の心地よいように、お前が変われ」というエゴイズムが透けて見えるからこそ、言われた側は息苦しさを感じ、反発する。当然の反応だ。
しかし、その矛先をくるりと反転させ、自分自身の心臓に向けた時、この言葉は全く別の輝きを帯びる。
「私は、こうありたい」 「俺は、こうあるべきだ」
それは、自分自身を律するための「大義」となる。
誰に言われるでもなく、自分自身の中に理想の姿を描き、それを規律として掲げる。それは一種の自己満足かもしれない。けれど、これほど気高く、美しい自己満足が他にあるだろうか。「自分がかっこいいと思うから、そう振る舞う」。動機はそれで十分だ。誰かのためでなくていい。社会のためでなくていい。ただ、自分が鏡を見た時に、その瞳に映る自分を愛せるかどうか。その一点においてのみ、私たちは「こうあるべきだ」という理想を徹底的に追求していい。
自分の中に確固たる「大義」を持つ人間は強い。 彼らは、他人の評価という強風に煽られても、決して根こそぎ倒れることがない。なぜなら、彼らの評価軸は常に自分自身の内側にあるからだ。
「今の振る舞いは、自分の美学に反していなかったか?」 「今の選択は、自分が掲げた大義に恥じないものだったか?」
そう自問自答し、自分で自分を裁くことができる人間は、他者からの冷笑や批判に対してすら、不敵に笑っていられる。「お前たちが何を言おうと、俺の美学はここにある」という前提があるからだ。彼らが迷いなく歩けるのは、道が平坦だからではない。自分という名のコンパスが、狂いなく北を指しているからだ。
もちろん、世界には無数の人間がいて、それぞれが異なる大義を抱えて生きている。 ある人の大義は「清貧」かもしれないし、ある人の大義は「享楽」かもしれない。「沈黙」を美徳とする者もいれば、「主張」こそが正義だと信じる者もいる。
時に、自分の信じる正義と、相手の信じる正義が真っ向から衝突することもあるだろう。
現代の「多様性」というスローガンは、ここで奇妙な解決策を強いてくる。「話し合おう」「理解し合おう」「寄り添おう」。まるで、異なる色を混ぜ合わせれば美しい絵ができると信じているかのように。
無理に寄り添う必要なんてないだろう。相手には相手の大義がある。それを認めるということは、必ずしも「受け入れて仲良くする」ことではない。「あなたはその道を生きるのですね。お気をつけて。では、私はこちらの道を行きます」と、互いの軌道を尊重し、静かに距離を置くことこそが、真の相互理解ではないだろうか。
合わない人間とは、合わない。この世界には重力のように変えられない相性というものが存在する。 それを無理にねじ曲げ、自分の色を殺してまで相手に合わせようとすること、あるいは相手の色を自分好みに塗り替えようとすることは、互いの大義に対する冒涜だ。
「距離を置く」という行為は、冷淡さの表れではない。むしろ、無用な衝突を避け、互いの尊厳を守るための、最も理性的で平和的な解決策だ。 無理をして寄り添い合い、互いに傷つけ合う関係に何の意味がある? 根本的に合わない相手から「私にあなたを理解させてよ」と擦り寄られることほど、ある種の屈辱を感じる瞬間はない。それは私の孤独という聖域への土足侵入に他ならないからだ。
私たちはもっと、孤独に対して堂々としていていい。それぞれの星が独自の軌道を描いているように、私たちもまた、自分だけの軌道を描いて回ればいいのだ。
だが、こうして大義を掲げて生きていても、夜の静寂の中でふと不安に襲われることがある。 「本当にこれでいいのだろうか」 「自分は間違っているのではないか」 「この大義は、ただの独りよがりではないか」
掲げた理想が高ければ高いほど、現実の自分との落差に眩暈がする。矛盾に苦しみ、自分の未熟さに反吐が出る夜もあるだろう。 そんな時は、思い切り悩めばいい。のたうち回ればいい。それは、あなたが自分の大義と真剣に向き合っている証拠だ。理想を持たない人間は、自分に失望することさえないのだから。
そして、もし心が折れそうになった時、「自分にはなりたいものなんてない」などと、嘘をついて逃げないでほしい。 「なりたい」という純粋な渇望が、「なれなかったらどうしよう」という恐怖や、「なれないかもしれない」という現実の重さに押し潰されているだけだ。その瓦礫の下には、まだ微かに熱を帯びた「理想」が埋まっているはずだ。
大義は、誰かに宣伝するためのポスターではない。 それは、自分自身の心の一番奥深く、誰の目にも触れない場所に立てる、一本の旗だ。
だから、恥ずかしがる必要はない。 誰かに否定されることを恐れる必要もない。なぜなら、その旗はあなただけのものだからだ。他人にその旗の色が見えることはない。彼らに見えるのは、ただ前を向いて歩くあなたの背中だけだ。
周りがどんなに騒がしくても、流行りの言葉が通り過ぎていっても、関係ない。 自分の中に、静かに、しかし猛々しく燃える炎を飼いならせ。 「こうあるべきだ」という理想の旗を、荒野のような心の大地に深く突き刺せ。 その旗がはためく音だけを信じて、進め。
誰にも理解されなくていい。 むしろ、誰にも理解させないという孤高こそが、その旗をより一層、鮮烈に輝かせるのだ。 自分だけの美学を貫き通すその姿は、きっと誰の目にも映らない場所で、最も美しく、ある種の芸術のように完成されていくのだろう。
それこそが、私たちが生きる上で手に入れられる、最高の「かっこよさ」なのだと思う。